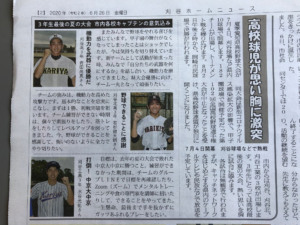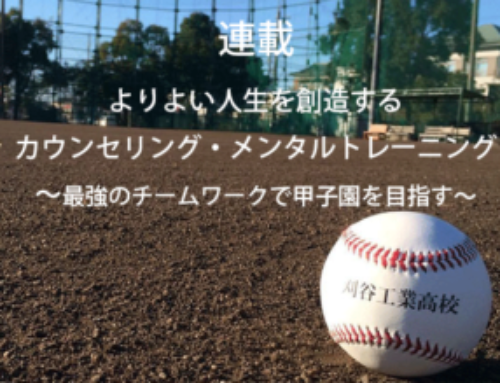第9章 コロナ危機に問われるもの
Ⅱ 部活動の本質とは何か
―愛知県独自大会の開催―
2020年5月20日、今夏の第102回全国高等学校野球選手権大会の中止が決定した。また、それに伴い、実質的な予選である各県の地方大会も中止となった。
すでに4月28日に全国高等学校総合体育大会(インターハイ)が中止になっていたことを考えれば、想定されたことではある。しかし、状況が好転して緊急事態宣言が解除されれば、夏の甲子園が開催できる可能性はあると信じていただけにショックは大きい。
3年生にとっては、3年生になって一度も公式戦をすることなく引退になる可能性もある。
夏の甲子園の出場枠は、東京、北海道から2校、45府県からは各1校の合計49校である。全国約4000校の野球部があるため、甲子園に出場できるのは約1%。
残りの99%の高校球児にとって、実際のところ地方大会が引退の花道である。
せめて地方大会だけでも開催してほしいと思っていたら、愛知県高野連はすぐに独自大会の方針を表明。
さらに6月5日には夏季愛知県高校野球大会という独自大会の概要が発表された。
大会はトーナメント方式。延長10回からタイブレークを行い、点差によるコールドは従来通りだが、降雨日没の場合は5回成立に変更。4回戦までは、地区ごとに地元の球場で実施。
ベンチ入りは20人で、試合ごとの入れ替えが可能。
選手のロッカー使用は禁止し、試合終了のたびにベンチを消毒。保護者のみの観戦を認める無観客試合、開会式や勝利校の校歌斉唱を取りやめるなど、コロナ対策を徹底。
私のようにメンタルトレーニングの外部コーチという立場では応援に行けないのは残念だが、選手たちのことを思うと、このような機会を用意していただいたことに感謝しかない。
―打倒!中京大中京―
刈谷工業は、非常に興味深いチームであり、新チームを結成以来、多くの高校球児が夢を見る甲子園を一度も目標とすることはなかった。
目標達成には、イメージする力が大切である。
刈谷工業にとっては、長い歴史の中で一度も甲子園に行ったことがない。
「目指せ!甲子園」という目標は、響きはよいが、メンタルトレーニングの観点から言えば、その目標が適切なのかは疑問である。
仮に刈谷工業が甲子園に出場するには、くじ運に恵まれる必要があるだろうし、自力に勝る強豪校との大一番での試合では、ラッキーが展開にならないと勝てないだろう。
運のような自分の力を超えたものを計算に入れてしまうと、本来やるべきことの焦点がぼやけてしまう。
「人事を尽くして天命を待つ」ということわざがあるように、まずやるべきことは自分の力を出し切ることである。120%自分たちの野球をやり切ったら、あとは静かに天命に任せるしかない。
刈谷工業の春季大会に対する目標は、西三河大会優勝であった。
地区大会で優勝するために倒さなければいけない高校、攻略しなければいけない投手は具体的にイメージできる。
西三河大会で優勝できる自力があるのであれば、県大会でも上位が狙えるだろう。
まずは春季大会で西三河大会優勝後、県大会でベスト8に進出し、夏の大会のシード権を得ることが目標であった。
結果として、春季大会は中止になってしまったが、刈谷工業にとっては、西三河大会優勝という目標は非常に理にかなったものであった。
そして、刈谷工業が掲げる最終目標は「打倒!中京大中京」である。
春の県大会での自分たちの戦いに自信を深め、夏の大会に中京大中京に挑戦するというのが思い描いていたシナリオである。
中京大中京には、全国ナンバーワンの呼び声もある高橋投手をはじめ、プロ注目のスター選手が多く在籍する全国でもトップレベルのチームである。
客観的に見れば、無謀な目標かもしれない。
しかし、刈谷工業にとっては、野球への取り組む姿勢を含めて、お手本としている憧れのチームであり、昨夏に愛知県大会の4回戦で敗れた相手でもある。
敗戦の悔しさをバネにリベンジしたいという心意気は大切である。
新型コロナウィルスの影響で、春の公式戦が全て中止になり、甲子園出場という道も閉ざされた中で、モチベーションの維持が非常に難しいところではあったが、「西三河大会優勝」「打倒!中京大中京」を掲げていた刈谷工業にとっては、愛知県の独自大会が開催されることで、再び目標に向けてチャレンジするチャンスをもらうことができた。
今回の愛知県の独自大会では、ベスト8までは地元の地区で地元の球場で試合をする。
つまり、西三河地区のチームとしか試合をしない。
まずは西三河地区のチームに連勝してベスト8を決め、中京大中京と試合をする。
これが刈谷工業の目標である。
一貫した明確な目標を掲げ、チーム一丸となって戦うのみである。
―休校後の練習再開―
6月1日に練習が再開。
長いブランクによる影響が心配されたが、選手たちの状態は良好。
野球ができることに感謝し、前向きに取り組むことができている。
6月23日には練習試合で私学四強の享栄と対戦。
練習試合ではあるが、1対0で勝利する。
さらには6月27日には昨年の春の選抜甲子園優勝校の東邦と練習試合。
相手は2年生主体のBチームであったが、4対3で勝利。
これで相手はベストメンバーではないが練習試合で中京大中京、愛工大名電、東邦、享栄の私学四強の全てに勝利した。
強豪校の1、2年生が主体のBチームは、次年度のチームを担う有望な下級生が出場しており、決して簡単に勝てる相手ではない。そんな相手への連勝は、大きな自信になるし、チームの調子は上昇傾向である。
愛知県の独自大会への期待が膨らむ。
―2020年夏の大会―
刈谷工業は7月5日に2回戦からのスタート。
対戦相手は知立。
打線のつながりが悪く、1対0のまま9回裏へ。
しかし、最後の最後に同点に追いつかれてしまう。
さらに1死満塁のサヨナラのピンチ。
ここを何とか踏ん張り、延長戦へ。
延長10回表からタイブレーク。
刈谷工業は猛攻を浴びせて一挙に6点をとり、一気に勝負を決める。
最終的には7対2で勝利した。
**
7月23日には3回戦で安城東と対戦。
刈谷工業は4回裏に1点を先制するが、8回表に同点に追いつかれてしまい、そのまま延長戦へ。
タイブレークとなった延長10回表に1点を失い、1対2。
しかし、10回裏、刈谷工業は土壇場で2点を返し、3対2で逆転サヨナラ勝ち。
見事4回戦進出を決める。
**
雨天中止などの影響で過密日程となり、翌日の7月24日に4回戦で吉良と対戦。
刈谷工業は3回裏に1点を先制、さらには5回裏に1点を追加する。
しかし、吉良の反撃により、8回表に一挙に3点を取られ、2対3の逆転を許す。
刈谷工業はすかさず8回裏に同点にするが、そのまま延長戦へ。
なんと3試合連続の延長戦タイブレーク。
1死満塁から始まるタイブレークでは、ギャンブル的な要素が大きい。
そのときの運を含めて、本当にちょっとした紙一重の差で勝負が決まってしまう。
勝利の女神が微笑んだのは、吉良の方であり、3対7で敗戦。
昨夏と同じく愛知県ベスト16を前に4回戦で刈谷工業の夏は終わった。
―なぜ本気で野球をやるのか―
新型コロナウィルスの感染拡大の問題によって、人類全体が大きな危機に直面している。
もしかしたら野球ができないまま引退することになるかもしれないという最悪の可能性も十分にありえる状況の中で、選手たちは野球ができることに喜びを感じ、改めて野球の大切さを痛感し、当たり前だと思っていた環境に感謝の気持ちを抱いたことだろう。
野球は決して楽だから楽しいというスポーツではない。
勝利を目指して本気で野球に取り組んできた人であれば、さまざまな困難こそがスポーツの価値や魅力を高めているということを理解できるはずである。
本気の高校野球生活の中には、人間的成長を遂げる要素がたくさんある。
長い人生の一部として考えた場合、コロナ危機に直面した苦しい時期での経験が自分自身を成長させるよい機会になったと思えるときがくる。
人生をマラソンに例えるならば、高校時代はまだ競技の序盤である。これから先に続く長い険しい道のりを進んでいく中で、高校野球に本気で取り組むことを通した学びをいかに生かすのかが重要である。
メンタルトレーニングで伝えてきたこと、それは野球のためだけのものではない。これからの人生を生き抜く上でも必ず役に立つことである。
刈谷工業での野球部の経験が必ず役に立つときがくるはずである。
先の見えない休校で練習ができなかった日々。
さらには多くの球児の夢だった甲子園がなくなった夏。
そうした状況にあっても、最後まで諦めずに全力プレーを続けた選手たちは素晴らしかったと思う。
こんな今だからこそ改めて本気で野球をやることの意義について考え直してみることが必要だと思う。
本気で野球に取り組むことで得ることは多い。
では、実際に野球を通して何を学んだのか、それを未来にどのように生かすのか、その答えは選手の数だけある。
ぜひ野球を愛する仲間同士で語り合ってほしい。
それぞれが感じる野球の素晴らしさを、自らの言葉で表現してほしい。
コロナ危機を通して、改めて、なぜ本気で野球をやるのか、その本質が問われていると思う。